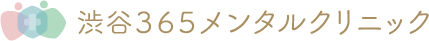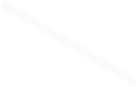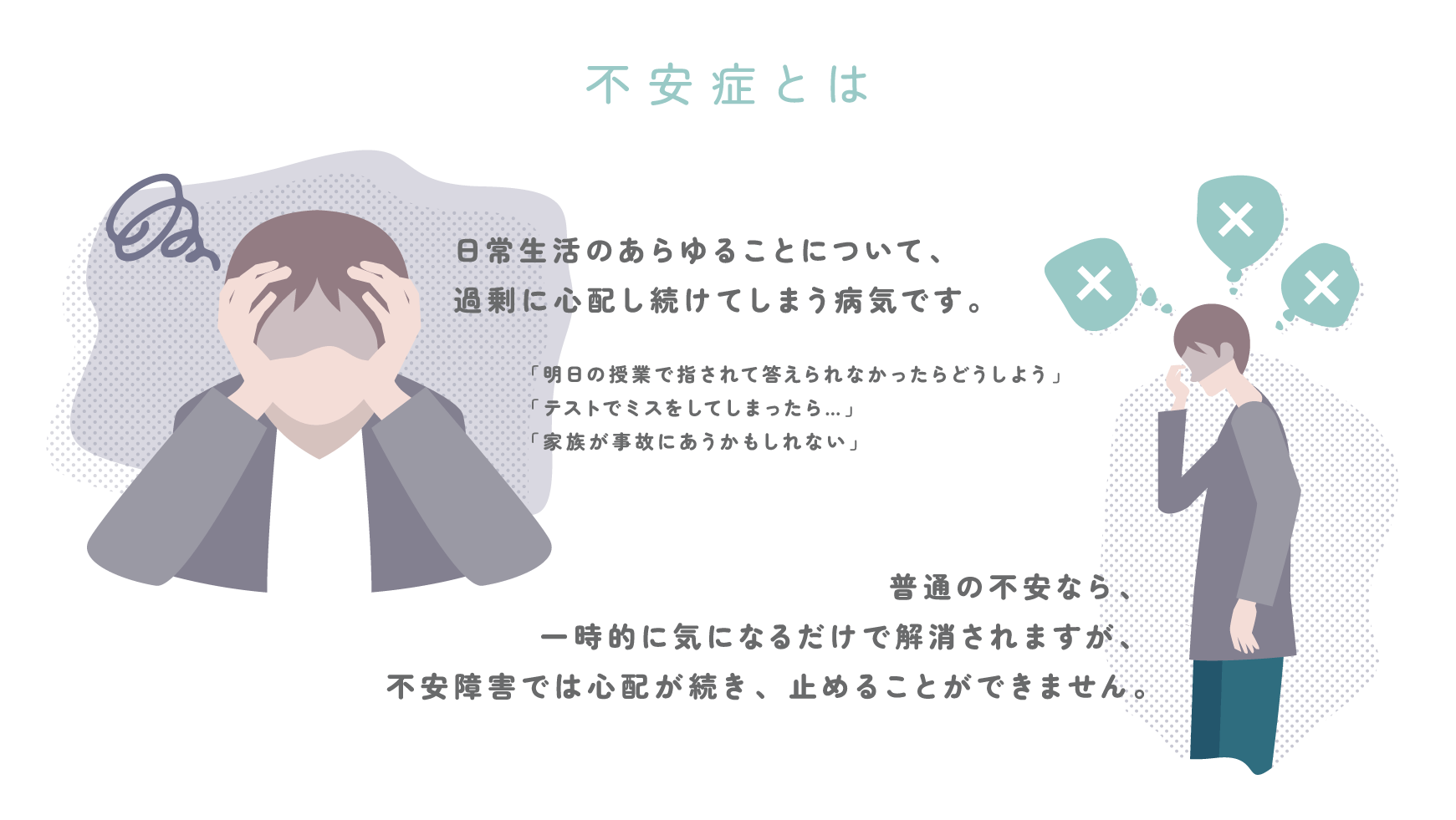特徴
不安障害には、次のような特徴があります。
1. 不安の範囲が広く、止まらない
一つのことではなく、「学校」「友達」「家族」「健康」「お金」など、多くのことが心配になる。
一つの不安が解決しても、また別の心配事が出てくる。
2. 心配をコントロールできない
「気にしすぎだ」と自分でわかっていても、不安を止めることができない。
友達や家族に「大丈夫だよ」と言われても、安心できないことが多い。
3. 身体の症状が現れる
不眠(心配事が頭から離れず、なかなか眠れない)
筋肉の緊張(肩こりや頭痛が続く)
疲れやすい(ずっと不安を抱えているため、エネルギーを消耗する)
イライラしやすい(些細なことでも怒りっぽくなる)
集中できない(心配ごとが多すぎて、勉強や作業に集中できない)
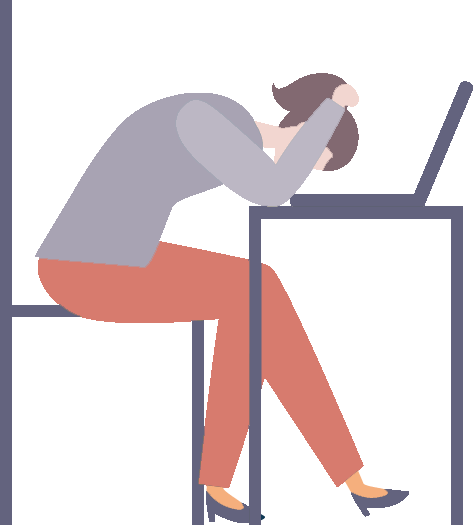
どんな人がなりやすいの?
不安障害は、誰にでも起こる可能性がありますが、特に次のような人は発症しやすいといわれています。
1. 真面目で責任感が強い人
「失敗してはいけない」「ちゃんとやらなければ」と強く思う人ほど、不安を感じやすい。
2. 環境の変化があった人
進学、転校、部活の変化など、大きな出来事があったときに不安が高まり、発症することがある。
3. 家族に心配性の人がいる
遺伝的な影響も関係しており、親や兄弟が不安を感じやすいと、自分もなりやすいといわれている。
4. ストレスを抱えやすい人
友人関係や勉強のプレッシャーが大きいと、心配することが増え、発症しやすくなる。
どうしたらいいの?
不安障害の不安を和らげるためには、次のような方法が有効です。
1. 不安を書き出して整理する
頭の中で考え続けると、不安がどんどん膨らむ。
紙に書き出して「今すぐ考えるべきこと」と「考えても仕方ないこと」に分けると、気持ちが整理しやすくなる。
2. 深呼吸やリラックスする習慣を作る
ゆっくり息を吸い、ゆっくり吐くことで、不安を和らげる。
ストレッチや軽い運動をすることで、体の緊張をほぐす。
3. 「今できること」に集中する
先のことを考えすぎると不安になるため、「今、自分ができることは何か?」に意識を向ける。

4. 誰かに相談する
家族や友達、先生に「最近、不安になることが多い」と話すだけでも気持ちが軽くなる。
必要に応じて、カウンセリングや専門医に相談する。
5. 専門家の治療を受ける
心療内科や精神科では、認知行動療法(考え方を変えるトレーニング)や、抗不安薬・抗うつ薬を使った治療を受けることができる。
早めに相談することで、症状を軽くすることができる。